日本創傷治癒学会 ‒ 50周年を迎えて -
東邦大学大学院医学研究科 先端医科学研究センター
組織修復・病態制御学
一般社団法人日本創傷治癒学会 理事長
赤坂 喜清
第1回日本創傷治癒学会は1971年に慶應義塾大学の耳鼻咽喉科鈴木安恒教授により研究会として開催されました。その後、慶應義塾大学の外科学教室に事務所が置かれ、阿部令彦教授の理事長のもと学術集会へと発展してきました。第1回創傷治癒研究会では鈴木安恒教授が冒頭で「創傷治癒というも問題は外科だけに限らず、非常に重要な問題だと思いますが、わりあいにやっていることが少ないので、(中略)、あまりその方に注意を向ける暇がなかった」と書いています。それから50年経過した現在でも創傷治癒の問題は大きな課題として取り扱われることなく、医学生教育の現場でも個々の疾患の講義に比べて創傷治癒を論じる授業時間はあまり多くありません。
創傷治癒は、原始人が狩猟で負った傷口を治すために始まった、太古の時代から継続する普遍的な学問です。戦争で不幸にも負傷した兵士を目の前にして出血を防ぎ感染症が合併しないよう早期に創部を閉鎖させることは極めて重要な課題でした。時代の進歩とともに創傷治癒の問題点は改善されてきました。しかしどの時代でも現象は変わらないものの、創傷治癒のメカニズムは解明されていない点が多くみられます。特に細胞群が一定の調和を保ちながら出現・消退を繰り返して規則正しく治癒が進行するメカニズムは不明です。我々にとって馴染み深い"線維芽細胞"においても、治癒過程で動員されるメカニズムは未だ不明です。
これまで50年間を振り返ると、本学会で活躍された先輩たちは「消化管吻合術再建」「難治性潰瘍治癒」の問題を精力的に解析してきました。種々のサイトカインがクローニングされると、いち早くサイトカインの治癒効果を基礎レベルで検討し、ヒト臨床応用の有効性を米国創傷治癒学会と連携して海外に発信してきました。また近年の幹細胞学の進歩に伴い、組織幹細胞を用いた治癒効果を組織工学で検討しヒト臨床応用を目指しました。さらに高齢化社会の訪れともに、重要な課題である「褥瘡」の治療法を創傷看護の立場から検討し、また下肢の糖尿病性潰瘍においてはチーム医療による実践法を報告してきました。このように、本学会は時代が求める重要な創傷治癒の問題を外科学、形成外科学、皮膚科学、看護学と基礎分野の先生方が「基礎と臨床」の融合を目指し、垣根を越えた討論から有効な治癒方法の開発に取り組んできました。
組織修復の破綻によって臓器は機能不全に陥り、やがて重篤な疾患の発症に至りますが、そのメカニズムには不明な点が多く残されています。最近、米国や日本では「生体組織の修復機構の生命現象」を解明する研究が注目されています。どんな疾患でも傷害を受けた臓器は瘢痕形成あるいは再生の両輪で修復が進行します。再生よりも瘢痕形成が主体のヒト臓器では、どの臓器でも瘢痕形成が最終的に辿る経路となっています。したがって今後、瘢痕形成のメカニズム解明と瘢痕抑制法の開発は本学会が目指す「基礎と臨床」の融合による、ヒトの様々な疾患における臓器傷害の機能不全を解消する新たな治療法開発に貢献できると考えています。
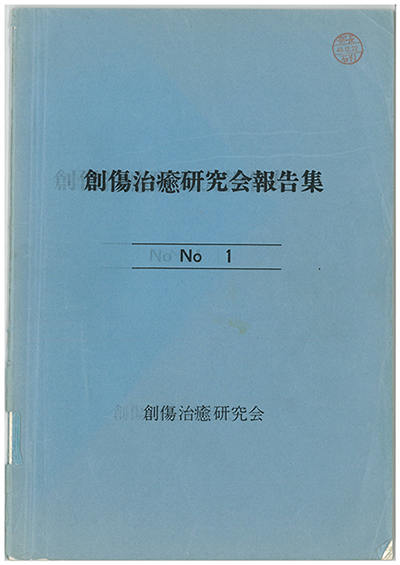
↑ 第1回創傷治癒研究会報告集の表紙(昭和46年7月26日)